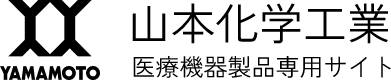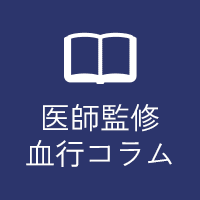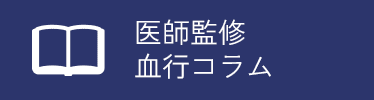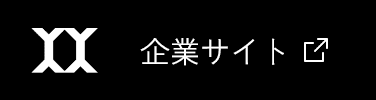花粉症の症状で血行不良に?原因や予防・解消方法を紹介
花粉症
内科・循環器内科

監修医師プロフィール

総合診療医 抗加齢医学 糖尿病内科 医療法人社団五良会理事長
五藤良将 医師
医療法人社団五良会の理事長および竹内内科小児科医院院長として、臨床医の立場から抗加齢医学や糖尿病治療に取り組む。製薬会社向け講演会のほか、全国放送のテレビ番組監修、医療専門誌やYahoo!ニュース等でのオンラインメディア監修も務め、幅広い医療知識を社会へ発信。患者の健康と生活の質向上を目指し、地域医療に貢献するための医療提供に注力している。
花粉症と体の血行について医学的な関連性はありません。ただし、花粉症の症状が血行不足に繋がる点もあります。花粉症と血行のつながりから予防と解消方法まで紹介していきます。
花粉症とは?
花粉症は、花粉に対するアレルギー反応で、鼻水・くしゃみ・目のかゆみなどの症状が特徴です。これは免疫系が花粉を異物と認識し、ヒスタミンなどの物質を放出することで炎症が起こるためです。この花粉症は医学では「季節性アレルギー性鼻炎」と呼ばれます。
花粉症の時期
花粉症になる花粉は約60種類あり、日本全国でほぼ一年を通して飛んでいます。
地域により時期の前後はありますが、花粉症の時期を一年にまとめました。
| 月 | 主な花粉 | 飛散状況 |
| 1月 | スギ・ハンノキ | 関東以西の一部でスギ花粉が飛び始め(例年並みかやや遅め)。ハンノキも少量飛散。 |
| 2月 | スギ・ハンノキ | スギ花粉の本格飛散開始(九州~関東で2月中旬頃から)。ピークは月末に近づく。 |
| 3月 | スギ・ヒノキ | スギ花粉ピーク(全国的に3月上旬~中旬)。 ヒノキ花粉が飛び始め(下旬から)。 |
| 4月 | ヒノキ・シラカバ | ヒノキ花粉ピーク(関東~近畿で4月上旬~中旬)。 シラカバが北海道で飛散開始。 |
| 5月 | シラカバ・イネ科 | シラカバ花粉ピーク(北海道で5月中旬)。 イネ科花粉が全国で増加。 |
| 6月 | イネ科 | イネ科花粉がピーク(全国的に6月上旬~中旬)。 一部地域で夏の花粉も。 |
| 7月 | イネ科 | イネ科花粉が減少傾向。地域によってはまだ少量飛散。 |
| 8月 | ブタクサ・ヨモギ | 秋花粉(ブタクサ、ヨモギなど)が飛び始め(8月下旬頃から)。 |
| 9月 | ブタクサ・ヨモギ | 秋花粉ピーク(9月中旬~下旬)。 特に東北地方~関東地方で顕著。 |
| 10月 | ブタクサ・ヨモギ | 秋花粉が継続(10月中旬までピーク、その後減少)。 |
| 11月 | なし | 花粉飛散はほぼ終了。 ただし、まれに残留花粉が観測されることも。 |
| 12月 | なし | 花粉飛散はほぼなし。次シーズンの準備期間。 |
何月ごろに花粉症の症状が出るか、自身で把握して時期による対策が必要になります。
花粉症になると血行不足になる?

花粉症は主に鼻と結膜に炎症を起こり、副鼻腔炎を引き起こします。副鼻腔炎は鼻水の量が増え、流れが悪くなることで溜まりやすくなります。酷い場合は呼吸がうまくできず、脳の血流が不十分になり軽い酸欠状態を起こすこともあります。
これを解消しようと体は咳やくしゃみを起こしますが、通常に比べ回数が非常に多くなり、身体に力が入ってしまい血行不良による肩のコリや筋肉痛になることもあります。
花粉症による血圧上昇
スイスの研究では花粉の飛散量が多くなるとアレルギー症状がある患者の血圧が上昇し、この症状は女性・肥満患者がより強くなるという報告もあります。
また、気管支喘息の人は花粉症による鼻水やくしゃみで喘息症状が悪化する場合もあります。
花粉症による血行不良の解消

マスクの着用は昔からの解消法とされており、花粉を防ぐという点では効果があります。
ただし、既に花粉症により鼻水やくしゃみなど副鼻腔炎の症状が出ている場合、過度なマスクの着用によって、軽い酸欠や血行が悪くなることもあります。
抗ヒスタミン薬の服用
花粉症の原因としてヒスタミン分泌があげられます、このヒスタミンは血管を拡張し鼻粘膜が膨張し鼻水の過剰分泌や鼻詰まりを引き起こします。これに抑えるのが抗ヒスタミン薬です。アレルギーの反応を抑えることが出来ますが、眠気や口が渇きやすいといった副作用がある場合もあります。
●第1世代 抗ヒスタミン薬
初期に開発された抗ヒスタミン薬のことを指します。効果は高く即効性もありますが、持続時間が短く副作用が出やすい欠点もあります。以前から鼻炎に効く薬は眠くなりやすいと言われていたのが、この世代になります。
●第2世代 抗ヒスタミン薬
現在主流となっているのが、第2世代の抗ヒスタミン薬です。即効性は第1世代に劣りますが、持続性が高いのが特徴です。近年の市販薬でも、この第2世代抗ヒスタミン薬は自動車運転時の禁止・制約の文章がないなど副作用が少ない事も特徴です。
以上のように、花粉症の治療には様々な種類の薬剤があり、それぞれに効果や副作用、使用上の注意点があります。自分に合った薬剤を選ぶためには、専門医の診断を受けることが大切です。
副鼻腔炎の症状を抑える
アレルギー症状の元を抑える以外に、鼻に溜まった膿などを出す事で解消する事も出来ます。抗菌薬の投与や鼻の吸い出しなどの治療となりますが、こちらは市販薬がありませんので耳鼻咽喉科での治療となります。花粉症の症状と合わせて医師への相談をお勧めします。
鼻の血行を改善する
蒸しタオルを鼻に当て、鼻や周辺の血行を解消することで一時的に症状を緩和できます。
・タオルをお湯につけ、絞ってから鼻に当てる
・水につけたタオルを500W20秒〜30秒ほど加熱して鼻に当てる
鼻にタオルを当て、数分安静にしましょう。
花粉症による血行不良の予防
予防法としては基本的には花粉との接触を避けることになります。また、体調が悪くなるとアレルギー反応も大きくなるため睡眠や食事など正しい生活習慣の維持も大切になります。
洗濯物を屋内干しにする
外干しの洗濯物には花粉がつきやすく、その花粉が鼻に入り花粉症が引き起こされます。花粉が多い日や特に日中は外に干さないようにしましょう。ウール素材など特に花粉が付着しやすい素材には注意が必要です。帰宅の際は上着など衣類を叩いてから自宅に入りましょう。
空気清浄機・フィルターの活用
花粉対応の空気清浄も有効です、花粉は空気より重いため床に溜まっていきます。床置きの空気清浄機がお勧めです。自宅が24時間換気システムの場合は、換気口に花粉対応のフィルターをつけておくのも良いでしょう。
ボディメンテナンスウェアを利用する
正しい生活習慣や運動習慣がなく、日頃から肩こりや体が冷えている人はより血行に影響があります。日頃の血行の改善にボディメンテナンスウェアの着用もお薦めです。ボディメンテナンスウェアには遠赤外線を放射する素材が使用されていて、着るだけで血行を促進し、疲労を回復したり、筋肉のコリを緩和させたりするのを助ける効果が期待できます。着るだけで日々の健康をサポートしてくれるという点が大きな特徴で、手間や時間がかからない手軽さがあります。
花粉症による血行不良|予防と対策
老若男女問わず世界中で多い花粉症ですが、特に女性・肥満の方ほど血行に影響があります。正しい生活・運動習慣による日常の血行の改善や自身の花粉症の時期の把握、それに伴った対策が必要です。花粉症の症状がひどい方は無理をせず、耳鼻咽喉科を受診し医師の診察を受けてください。
監修医師プロフィール

総合診療医 抗加齢医学 糖尿病内科 医療法人社団五良会理事長
五藤良将 医師
医療法人社団五良会の理事長および竹内内科小児科医院院長として、臨床医の立場から抗加齢医学や糖尿病治療に取り組む。製薬会社向け講演会のほか、全国放送のテレビ番組監修、医療専門誌やYahoo!ニュース等でのオンラインメディア監修も務め、幅広い医療知識を社会へ発信。患者の健康と生活の質向上を目指し、地域医療に貢献するための医療提供に注力している。